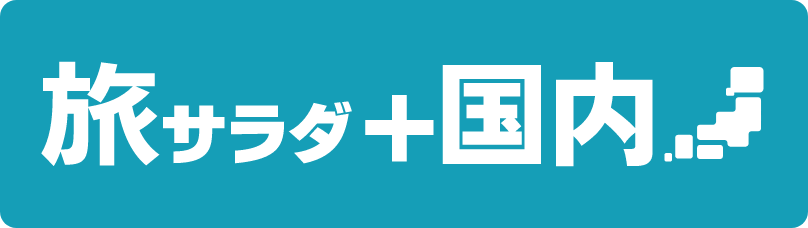中国・寺院ランキングRANKING
-
1位

耕三寺博物館(耕三寺)
生口島(いくちじま)にある耕三寺は「西の日光」と称され、壮大な伽藍の建造物群が見もの。建物のほかにも「潮聲閣(ちょうせいかく)コレクション」や「未来心の丘」など見どころが多く、「しまなみ海道」で屈指の観光スポットとなっている。
-
2位

三徳山 三佛寺奥院 投入堂
標高900メートルの三徳山に境内がある三徳山三佛寺。その奥院である投入堂は切り立つ絶壁にせり出すように建てられた建築物で、国宝に指定されている。かつて数々の不可思議な事績を残した役行者(えんのぎょうじゃ)が法力でお堂を手のひらに乗るほどに小さくし、断崖絶壁の岩窟に投げ入れたと伝わるお堂だ。山道は非常に危険で事故も多いため、入山の際は服装と靴のチェックを受ける必要がある。ふもとにある「投入堂遙拝所」から望遠鏡で見るのがおすすめだ。
-
3位

国宝瑠璃光寺五重塔
山口市の香山公園内にある五重塔。現存する五重塔の中で10番目に古く、日本三名塔のひとつに数えられる。嘉吉2年(1442)頃に建立。当時全盛期を迎えていた大内文化の傑作であり、国宝に指定されている。高さは31.2m。勾配のゆるい優美な檜皮葺屋根が特徴で、桜や楓の裏山を背に格別の風情を感じさせる。夜間のライトアップも必見。
-
4位

阿伏兎観音
沼隈半島の南端にある阿伏兎観音は海面から高さ約15mの断崖の上にあり、朱色に輝く建物は自然と見事に調和している。航海の安全のほか、子授けと安産の祈願所として有名だ。
-
5位

出雲大社 宝物殿
出雲大社の境内にある宝物殿(神祜殿)では昭和56年(1981)の竣功以来貴重な宝物の数々を展示・公開している。「神祜」とは「神の助け」を意味する言葉。平成12年(2000)には平成の大遷宮を記念した改修工事により展示施設を刷新。平成29年(2017)のリニューアルオープンにあわせて御本殿の中心を支えていた「心御柱」も一般公開している。
-
6位

千光寺
尾道市の千光寺公園内にある寺院。寺伝によれば大同元年(806)、弘法大師の開基。朱塗りの本堂は舞台造りという珍しい構造で、鐘楼とあわせて尾道を象徴する建物。本堂横の巨岩「玉の石」の上には、かつて光を輝く宝玉が置かれ海上を照らしていたという伝説がある。境内からは、尾道の市街地と瀬戸内海を一望する絶景を満喫できる。
-
7位

神勝寺 禅と庭のミュージアム
広島県福山市にある寺院の広大な敷地に造られた、禅の世界を体感できるミュージアム。滋賀県から移築した17世紀の堂宇や復元された千利休の茶室、禅庭などを配し様々な角度から禅を五感で体験できるようになっている。アートパビリオン「洸庭」では他にはない禅の世界観を体感できる。200点を超える白隠コレクションも見どころ。
-
8位

月照寺
徳川家康の孫にあたる初代・直政から9代・斉斎(なりよし)までの墓がある、松平家の菩提寺。花の寺としても知られ、冬はサザンカとツバキ、春の桜のほか、初夏のアジサイ、晩秋の紅葉も美しい。
-
9位

備中国分寺
総社市南部の丘陵地にある備中国分寺は、奈良時代の聖武天皇が全国に建立させた寺のひとつ。その寺院跡に江戸時代に建造されたのが五重塔で、田畑のなかに立つ姿は吉備路のシンボルとして人気が高い。
-
10位

最上稲荷
日蓮宗の寺で、正式名称は「最上稲荷山妙教寺」。延暦4年(785)頃に報恩大師により開かれたとされ、日本三大稲荷のひとつと言われる名刹である。明治の廃仏毀釈の被害を受けず、「神仏習合」の祭祀形態を認められた寺であり、仏教の流れを汲む珍しい稲荷。寺でありながら鳥居があり、本殿は神宮形式。商売繁盛や開運、交通安全など様々なご利益があるといわれ、古くから信仰を集めている。
-
11位

羅漢寺 五百羅漢
大田市大森町の天恩山五百羅漢寺にある石仏。2つの石窟の中に250体ずつ安置されている五百羅漢像は、元文年間(1736-1740)の発願から二十数年かけて完成したもので、石見銀山で亡くなった人々の霊や先祖の霊の供養を目的に建立されたといわれている。「石見銀山遺跡とその文化的景観」の一部としてユネスコの世界遺産に登録されているほか、国の史跡にも指定されている。
-
12位

天寧寺
尾道駅から徒歩約15分の立地にある曹洞宗の寺で、貞治6年(1367)に足利義詮の寄進により普明国師が開山したと言われている。義詮が五重塔として建立し、後に三重塔として改められた「海雲塔」は、国の重要文化財。塔越しに街並みと海を見下ろす風景は、尾道を代表する景観である。羅漢堂に安置された526体の五百羅漢は必見。本堂内の左の「さすり仏さん」は、患っている場所と同じ部分を撫でると病気平癒の御利益があると言われている。4月から5月にかけては、境内の枝垂れ桜や牡丹が美しく咲き乱れる。
-
13位

世界平和記念聖堂
広島市中区にある「カトリック幟町教会」の聖堂で、原爆犠牲者の慰霊と平和のシンボルとして昭和29年(1954)に完成。自身も被爆したフーゴー・ラッサール神父が発案し、ローマ教皇をはじめ世界各国からの協力により建設された。戦後の新しい時代に相応しいモダンかつ荘厳な建築デザインで、設計は村野藤吾氏。建物は国の重要文化財に指定されている。
-
14位

曹洞宗 巨嶽山 正福寺
境港市中野町にある寺院。「ゲゲゲの鬼太郎」などで知られる漫画家・水木しげるの妖怪画の原点とされる「六道絵 地獄極楽絵」を所蔵している。地獄絵3枚、極楽絵1枚からなるもので、水木少年にこの世ではない別の世界の存在を教え、その作品世界に大きな影響を与えたとされる。境内には妖怪漫画の巨匠の偉業を称える「水木しげる記念碑」や松尾芭蕉の句碑もある。
-
15位

天寧寺海雲塔
足利義詮の寄進により普明国師が開山したと伝わる曹洞宗の寺院・天寧寺の境内に建つ三重塔。嘉慶2年(1388)に義詮が建立した当時は五重塔であったが、元禄5年(1692)に上部2層を除いて三重塔に改めたと言われている。国の重要文化財に指定されており、尾道の街並みと海と調和した風景は、尾道を代表する景観として知られている。最寄は尾道駅。
-
16位

洞春寺
山口市水の上町にある、毛利元就の菩提寺として知られる寺院。かつて大内盛見が建立した国清寺の跡地でもあり、その名残として重要文化財である四脚門の山門が残る。大内氏の滅亡後、元亀3年(1572)に安芸の国吉田の城内に洞春寺が創建され、毛利家とともに移転を繰り返した後、明治元年(1868)に現在の地に移された。山門とともに重要文化財に指定されている観音堂は、大内氏ゆかりの滝の観音寺から移建されたもので、花頭窓や桟唐戸などが美しい唐様の建物。寺内では、メディアで有名になった看板犬「マル住職」が参拝者を出迎える。
-
17位

功山寺
下関市長府川端1丁目にある寺。曹洞宗の寺で「千手観音菩薩」を本尊としている。創建は1327年で、仏殿は鎌倉時代の禅宗様建築を代表するものとして、国宝に指定されている。幾度となく歴史の舞台になった場所としても知られており、境内には馬上の高杉晋作像があることから、多くの歴史ファンが訪れるスポットとしても知られている。
-
18位

興禅寺
三禅宗のひとつ、黄檗宗の寺院。鳥取藩主・池田家の菩提寺として高い寺格を持ち、陸奥伊達家の大年寺、長門毛利家の東光寺と並んで「黄檗三叢林」と称されている。しっとりとした趣の見事な書院庭園は寛永21年(1632)の創建と共に作庭されたもの。文化文政期の華やかさを持ちつつ大名の御霊屋として格調ある空間と由緒を伝える本堂は国登録有形文化財に指定されている。剣豪・臼井本覚や渡辺数馬の墓、県指定保護文化財のキリシタン灯籠など見どころも多い。
-
19位

大願寺
「日本三大弁財天」の「嚴島弁財天」がある大願寺。今はこぢんまりした寺だが、古くから嚴島神社との関係が深く、かつては厳島伽藍の中心となる大寺院だった。弁財天像ばかりか、宮島の貴重な仏像がここに集まっている。
-
20位

大本山 大聖院
廿日市市宮島町にある真言宗御室派の大本山であり、宮島で最も歴史の古い寺院。806年に宮島へ渡った空海が開いたと伝えられている。かつては厳島神社の法会祭事を司る別当寺であり、皇室とのゆかりも深い。観音堂の本尊である十一面観世音菩薩ほか多数の仏像が安置されており、全国で唯一「三鬼大権現」を祀る寺でもある。対岸の町並みを望める静かな環境で、紅葉の名所としても有名。
-
21位

観音院庭園
鳥取県鳥取市上町にある寺院で、かつては鳥取藩主・池田家の祈願所であった。中国観音霊場32番札所。本尊は聖観世音菩薩像で、移転のたびに大きな寺の本尊となったことから「出世観音」として信仰を集めている。慶安3年(1650)から10年かけて造営された国指定名勝の観音院庭園は、雄大な池を中心に傾斜や石組、植木を配した池泉観賞式庭園。
-
22位

天柱山 頼久寺
岡山県の備中エリアで唯一の城下町、高梁市。国指定の名勝となっている頼久寺は、茶人としても知られる備中国奉行の小堀遠州(こぼりえんしゅう)の作庭と伝わる庭園が有名だ。
-
23位

山口サビエル記念聖堂
緑に囲まれた小高い丘の上に立つ山口サビエル記念聖堂。2本の白亜の塔が街を見下ろすモダンなデザインの聖堂は、山口市のシンボル的存在だ。ステンドグラスが美しい祭壇や展示スペースなど、見どころもいっぱい。
-
24位

瑠璃光寺
日本三大名塔のひとつに数えられる国宝の五重塔が有名で、青空に映える美しいシルエットは必見だ。境内は香山公園と呼ばれ、春には桜、秋には紅葉が美しく、西の京・山口を代表する観光スポットとなっている。
-
25位

西方寺普明閣
竹原市の町並み保存地区にある浄土宗の寺院・西方寺の観音堂。以前この地にあった禅寺・妙法寺の本尊「木造十一面観音立像」が安置されている。宝暦8年(1758)に京都・清水寺を参考に建築されたといわれ、本瓦葺き二重屋根の舞台造りが特徴。普明閣からは竹原の町や瀬戸内海を一望することができ、多くの観光客が訪れる人気スポットになっている。
-
26位

一畑寺(一畑薬師)
一畑薬師教団の総本山。創開は平安時代寛平6年(894)で、一畑山の麓、日本海の赤浦海中から漁師の与市が引き上げた薬師如来をご本尊としておまつりしたのが始まり。眼病平癒にご利益があると言われ、「目のお薬師さま」として古くから信仰を集めてきた。1300段に及ぶ石段の参道があることでも知られる。
-
27位

大山寺 本堂
開創は奈良時代、平安末期から比叡山や高野山にも劣らない隆盛を誇った古刹。山岳仏教の修験場としても栄えたことでも知られる。大山の豊かな自然に抱かれおごそかな雰囲気の漂う石段を上がり、ゆっくり参拝したい。
-
28位

黄檗宗 護国山 東光寺
萩市にある黄檗宗の寺院であり、旧萩藩藩主・毛利家の菩提寺。元禄4年(1691)に3代藩主・毛利吉就が建立し、毛利氏廟所には、5代・7代・9代・11代の藩主および夫人や側室など一族の墓がある。また、境内には重要文化財の総門・大雄宝殿・鐘楼など、見ごたえある中国風の建築物が多数点在。
-
29位

佛通寺
三原市高坂町許山にある寺院。釈迦如来を本尊とした臨済宗の寺で、1397年に創建された。境内には国の重要文化財指定の地蔵堂や、画家の雪舟が滞在したと伝わる庵の跡などがあり、四季ごとに美しい自然の景色も楽しめる。特に秋は紅葉の名所としても知られており、夜にはライトアップも行われ、多くの参拝客で賑わう。
-
30位

三瀧寺
広島市西区にある寺院。高野山真言宗の寺院で、三滝山の中腹に位置する。809年に空海により創建されたと伝えられており、境内には水流の異なる3つの滝がある。原爆犠牲者の供養のために建てられた境内の多宝塔は、和歌山の広八幡神社から移築され、重要文化財に指定されている。塔の中には国の重要文化財である「木造阿弥陀如来坐像」も安置されている。また、春や秋には桜や紅葉の名所として賑わいを見せる。
-
8位

月照寺
徳川家康の孫にあたる初代・直政から9代・斉斎(なりよし)までの墓がある、松平家の菩提寺。花の寺としても知られ、冬はサザンカとツバキ、春の桜のほか、初夏のアジサイ、晩秋の紅葉も美しい。
-
9位

備中国分寺
総社市南部の丘陵地にある備中国分寺は、奈良時代の聖武天皇が全国に建立させた寺のひとつ。その寺院跡に江戸時代に建造されたのが五重塔で、田畑のなかに立つ姿は吉備路のシンボルとして人気が高い。
-
10位

最上稲荷
日蓮宗の寺で、正式名称は「最上稲荷山妙教寺」。延暦4年(785)頃に報恩大師により開かれたとされ、日本三大稲荷のひとつと言われる名刹である。明治の廃仏毀釈の被害を受けず、「神仏習合」の祭祀形態を認められた寺であり、仏教の流れを汲む珍しい稲荷。寺でありながら鳥居があり、本殿は神宮形式。商売繁盛や開運、交通安全など様々なご利益があるといわれ、古くから信仰を集めている。
-
11位

羅漢寺 五百羅漢
大田市大森町の天恩山五百羅漢寺にある石仏。2つの石窟の中に250体ずつ安置されている五百羅漢像は、元文年間(1736-1740)の発願から二十数年かけて完成したもので、石見銀山で亡くなった人々の霊や先祖の霊の供養を目的に建立されたといわれている。「石見銀山遺跡とその文化的景観」の一部としてユネスコの世界遺産に登録されているほか、国の史跡にも指定されている。
-
12位

天寧寺
尾道駅から徒歩約15分の立地にある曹洞宗の寺で、貞治6年(1367)に足利義詮の寄進により普明国師が開山したと言われている。義詮が五重塔として建立し、後に三重塔として改められた「海雲塔」は、国の重要文化財。塔越しに街並みと海を見下ろす風景は、尾道を代表する景観である。羅漢堂に安置された526体の五百羅漢は必見。本堂内の左の「さすり仏さん」は、患っている場所と同じ部分を撫でると病気平癒の御利益があると言われている。4月から5月にかけては、境内の枝垂れ桜や牡丹が美しく咲き乱れる。
-
13位

世界平和記念聖堂
広島市中区にある「カトリック幟町教会」の聖堂で、原爆犠牲者の慰霊と平和のシンボルとして昭和29年(1954)に完成。自身も被爆したフーゴー・ラッサール神父が発案し、ローマ教皇をはじめ世界各国からの協力により建設された。戦後の新しい時代に相応しいモダンかつ荘厳な建築デザインで、設計は村野藤吾氏。建物は国の重要文化財に指定されている。
-
14位

曹洞宗 巨嶽山 正福寺
境港市中野町にある寺院。「ゲゲゲの鬼太郎」などで知られる漫画家・水木しげるの妖怪画の原点とされる「六道絵 地獄極楽絵」を所蔵している。地獄絵3枚、極楽絵1枚からなるもので、水木少年にこの世ではない別の世界の存在を教え、その作品世界に大きな影響を与えたとされる。境内には妖怪漫画の巨匠の偉業を称える「水木しげる記念碑」や松尾芭蕉の句碑もある。
-
15位

天寧寺海雲塔
足利義詮の寄進により普明国師が開山したと伝わる曹洞宗の寺院・天寧寺の境内に建つ三重塔。嘉慶2年(1388)に義詮が建立した当時は五重塔であったが、元禄5年(1692)に上部2層を除いて三重塔に改めたと言われている。国の重要文化財に指定されており、尾道の街並みと海と調和した風景は、尾道を代表する景観として知られている。最寄は尾道駅。
-
16位

洞春寺
山口市水の上町にある、毛利元就の菩提寺として知られる寺院。かつて大内盛見が建立した国清寺の跡地でもあり、その名残として重要文化財である四脚門の山門が残る。大内氏の滅亡後、元亀3年(1572)に安芸の国吉田の城内に洞春寺が創建され、毛利家とともに移転を繰り返した後、明治元年(1868)に現在の地に移された。山門とともに重要文化財に指定されている観音堂は、大内氏ゆかりの滝の観音寺から移建されたもので、花頭窓や桟唐戸などが美しい唐様の建物。寺内では、メディアで有名になった看板犬「マル住職」が参拝者を出迎える。
-
17位

功山寺
下関市長府川端1丁目にある寺。曹洞宗の寺で「千手観音菩薩」を本尊としている。創建は1327年で、仏殿は鎌倉時代の禅宗様建築を代表するものとして、国宝に指定されている。幾度となく歴史の舞台になった場所としても知られており、境内には馬上の高杉晋作像があることから、多くの歴史ファンが訪れるスポットとしても知られている。
-
18位

興禅寺
三禅宗のひとつ、黄檗宗の寺院。鳥取藩主・池田家の菩提寺として高い寺格を持ち、陸奥伊達家の大年寺、長門毛利家の東光寺と並んで「黄檗三叢林」と称されている。しっとりとした趣の見事な書院庭園は寛永21年(1632)の創建と共に作庭されたもの。文化文政期の華やかさを持ちつつ大名の御霊屋として格調ある空間と由緒を伝える本堂は国登録有形文化財に指定されている。剣豪・臼井本覚や渡辺数馬の墓、県指定保護文化財のキリシタン灯籠など見どころも多い。
-
19位

大願寺
「日本三大弁財天」の「嚴島弁財天」がある大願寺。今はこぢんまりした寺だが、古くから嚴島神社との関係が深く、かつては厳島伽藍の中心となる大寺院だった。弁財天像ばかりか、宮島の貴重な仏像がここに集まっている。
-
20位

大本山 大聖院
廿日市市宮島町にある真言宗御室派の大本山であり、宮島で最も歴史の古い寺院。806年に宮島へ渡った空海が開いたと伝えられている。かつては厳島神社の法会祭事を司る別当寺であり、皇室とのゆかりも深い。観音堂の本尊である十一面観世音菩薩ほか多数の仏像が安置されており、全国で唯一「三鬼大権現」を祀る寺でもある。対岸の町並みを望める静かな環境で、紅葉の名所としても有名。
-
21位

観音院庭園
鳥取県鳥取市上町にある寺院で、かつては鳥取藩主・池田家の祈願所であった。中国観音霊場32番札所。本尊は聖観世音菩薩像で、移転のたびに大きな寺の本尊となったことから「出世観音」として信仰を集めている。慶安3年(1650)から10年かけて造営された国指定名勝の観音院庭園は、雄大な池を中心に傾斜や石組、植木を配した池泉観賞式庭園。
-
22位

天柱山 頼久寺
岡山県の備中エリアで唯一の城下町、高梁市。国指定の名勝となっている頼久寺は、茶人としても知られる備中国奉行の小堀遠州(こぼりえんしゅう)の作庭と伝わる庭園が有名だ。
-
23位

山口サビエル記念聖堂
緑に囲まれた小高い丘の上に立つ山口サビエル記念聖堂。2本の白亜の塔が街を見下ろすモダンなデザインの聖堂は、山口市のシンボル的存在だ。ステンドグラスが美しい祭壇や展示スペースなど、見どころもいっぱい。
-
24位

瑠璃光寺
日本三大名塔のひとつに数えられる国宝の五重塔が有名で、青空に映える美しいシルエットは必見だ。境内は香山公園と呼ばれ、春には桜、秋には紅葉が美しく、西の京・山口を代表する観光スポットとなっている。
-
25位

西方寺普明閣
竹原市の町並み保存地区にある浄土宗の寺院・西方寺の観音堂。以前この地にあった禅寺・妙法寺の本尊「木造十一面観音立像」が安置されている。宝暦8年(1758)に京都・清水寺を参考に建築されたといわれ、本瓦葺き二重屋根の舞台造りが特徴。普明閣からは竹原の町や瀬戸内海を一望することができ、多くの観光客が訪れる人気スポットになっている。
-
26位

一畑寺(一畑薬師)
一畑薬師教団の総本山。創開は平安時代寛平6年(894)で、一畑山の麓、日本海の赤浦海中から漁師の与市が引き上げた薬師如来をご本尊としておまつりしたのが始まり。眼病平癒にご利益があると言われ、「目のお薬師さま」として古くから信仰を集めてきた。1300段に及ぶ石段の参道があることでも知られる。
-
27位

大山寺 本堂
開創は奈良時代、平安末期から比叡山や高野山にも劣らない隆盛を誇った古刹。山岳仏教の修験場としても栄えたことでも知られる。大山の豊かな自然に抱かれおごそかな雰囲気の漂う石段を上がり、ゆっくり参拝したい。
-
28位

黄檗宗 護国山 東光寺
萩市にある黄檗宗の寺院であり、旧萩藩藩主・毛利家の菩提寺。元禄4年(1691)に3代藩主・毛利吉就が建立し、毛利氏廟所には、5代・7代・9代・11代の藩主および夫人や側室など一族の墓がある。また、境内には重要文化財の総門・大雄宝殿・鐘楼など、見ごたえある中国風の建築物が多数点在。
-
29位

佛通寺
三原市高坂町許山にある寺院。釈迦如来を本尊とした臨済宗の寺で、1397年に創建された。境内には国の重要文化財指定の地蔵堂や、画家の雪舟が滞在したと伝わる庵の跡などがあり、四季ごとに美しい自然の景色も楽しめる。特に秋は紅葉の名所としても知られており、夜にはライトアップも行われ、多くの参拝客で賑わう。
-
30位

三瀧寺
広島市西区にある寺院。高野山真言宗の寺院で、三滝山の中腹に位置する。809年に空海により創建されたと伝えられており、境内には水流の異なる3つの滝がある。原爆犠牲者の供養のために建てられた境内の多宝塔は、和歌山の広八幡神社から移築され、重要文化財に指定されている。塔の中には国の重要文化財である「木造阿弥陀如来坐像」も安置されている。また、春や秋には桜や紅葉の名所として賑わいを見せる。
人気の記事 POPULAR NEWS
-

神戸の人気観光スポットおすすめ30選|外せない定番・名所から穴場まで見どころ満載の観光地を紹介
おでかけ 兵庫 旅行 -

新潟の人気観光スポットおすすめ20選|外せない定番・名所から穴場まで見どころ満載の観光地を紹介
おでかけ 中部 新潟 -

長崎の人気観光スポットおすすめ30選|外せない定番・名所から穴場まで見どころ満載の観光地を紹介
おでかけ 九州 旅行 -

宮崎の人気観光スポットおすすめ20選|外せない定番・名所から穴場まで見どころ満載の観光地を紹介
おでかけ 九州 宮崎 -

滋賀の人気観光スポットおすすめ20選|外せない定番・名所から穴場まで見どころ満載の観光地を紹介
おでかけ 旅行 滋賀 -

鳥取の人気観光スポットおすすめ20選|外せない定番・名所から穴場まで見どころ満載の観光地を紹介
おでかけ 中国 旅行 -

秋田の人気観光スポットおすすめ20選|外せない定番・名所から穴場まで見どころ満載の観光地を紹介
おでかけ 旅行 東北 -

和歌山の人気観光スポットおすすめ20選|外せない定番・名所から穴場まで見どころ満載の観光地を紹介
おでかけ 和歌山 旅行