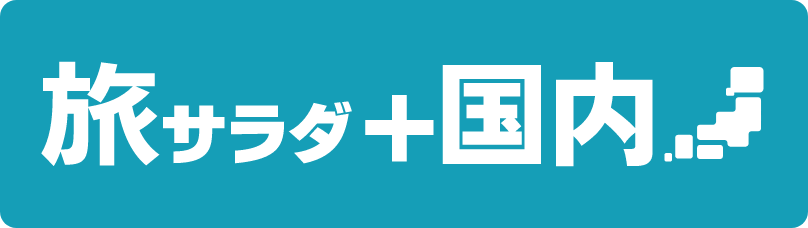和歌山県・寺院ランキングRANKING
-
1位

熊野本宮大社
熊野信仰の総本山、熊野本宮大社。こちらなしに世界遺産「紀伊山地の霊場と参詣道」を語ることはできない。身分や老若男女、浄不浄を問わずすべての人に救いを差し伸べた熊野本宮大社にはいったい何があるのだろうか。
-
2位

紀三井寺(紀三井山金剛宝寺護国院)
緑の山腹に映える朱塗りの塔がそびえる和歌山市の紀三井寺は、遠くからも目立つ寺院だ。一年を通して和歌浦湾の眺望を楽しめ、春には桜の名所として有名。本堂までの231段の石段を、良縁を願いながら上ってみよう。
-
3位

慈尊院
平成16年(2004)に世界遺産「紀伊山地の霊場と参詣道」の一部として登録された慈尊院弥勒堂は、当時女人禁制の高野山に入山できなかった空海の母・玉依御前が滞在したことから、子宝や安産を願う「女人高野」として知られる。また御本尊「木造弥勒仏坐像」は平安時代の代表的な彫像で、昭和38年(1963)、国宝に指定された。約100体ものお地蔵様や、県指定文化財の土塀などみどころ満載だ。南海高野線「九度山」駅から徒歩約20分。
-
4位

金剛峯寺
真言密教の根本道場として、弘法大師によって開かれた日本仏教の聖地・高野山。高野山は全体をひとつの寺院として見立てていた「一山境内地」とされ、その総本山である金剛峯寺には、大主殿(だいしゅでん)や石庭、襖絵など多くの見どころが存在する。
-
5位

不動堂
高野山の中門を抜けた壇上伽藍の東側にある縋破風造りの建物。まるで平安貴族の邸宅のような雰囲気が感じられるが、これは高野山に建つ寺院のなかでも異質。また建立された目的が不明、不動堂なのに護摩壇の形跡がないなど数々の不思議に包まれている。創建は鎌倉時代の1198年。明治32年(1899)に国宝に指定され明治41年(1908)の修理で現在の場所に移築。高野山はたびたび大火災に見舞われているが、もともと不動堂があった場所には類焼が及ぶことはなかった。そのため現在も創建当時の姿で見ることができる稀有な建物でもある。
-
6位

根本大塔
根本大塔とは真言密教の根本道場におけるシンボルとして建設されたもの。高野山金剛峯寺の壇上にある根本大塔は空海が高野山を開創した時より建立に着手し、887年ごろに完成したと伝えられる。現在の塔は昭和12年(1937)空海の入定1100年を記念して再建。16間四面、高さ約50mからなる2層の多宝塔様式が特徴である。見どころは堂内そのものが立体の曼荼羅として構成された作りにある。主尊の胎蔵界大日如来を中心に周囲を金剛界の四仏が取り囲む。16本の柱には十六大菩薩が、四隅の壁には八祖像が描かれている。
-
7位

金剛峯寺 阿字観
高野山真言宗の総本山、金剛峯寺では、参拝客向けに体験講座を提供している。その中でも「阿字観」は、大宇宙を象徴する「ア」の字を前に行う真言宗の呼吸法・瞑想法で、僧侶の指導のもと宇宙や命を思索する。体験は売店で先着順、定員10名、小学生以上対象、1回1000円で、金・土・日・月曜の1日4回、約1時間。別途内拝料が必要だ。
-
8位

金剛三昧院
北条政子が夫・源頼朝と息子・実朝の菩提を弔うために建立した「金剛三昧院」は、国宝の多宝塔をはじめ数々の文化財を擁しており、世界遺産 「紀伊山地の霊場と参詣道」の構成資産ともなっている。鎌倉時代そのままの荘厳な雰囲気は参拝客を圧倒する。南海電鉄「極楽橋駅」からケーブルカーで約5分。
-
9位

東光寺
湯の峰温泉にある天台宗の寺院。高さ約3mの本尊「湯峯薬師」は、温泉の源泉の周囲で湯の花が自然に積って薬師如来の形となったものだと伝わっている。約1800年前、裸形上人が薬師如来の胸に空いた穴から温泉が湧きだしているのを見出したという。毎年1月8日には、「八日薬師祭」が行われ、温泉の湯を献湯し、湯の峰温泉の繁栄と参拝者の諸願成就を祈願する。
-
10位

道成寺
日高川町鐘巻にある大宝元年(701)創建の和歌山県最古の寺院。講堂の本尊である千手観音像は1300年以上の歴史を誇る日本でも最も古いもののひとつ。これを含め宝佛殿では国宝3点、重要文化財11点、県指定文化財4点の貴重な仏像を年間を通じて参拝することができる。
-
11位

救馬溪観音
南紀白浜温泉街から車で約25分の所に鎮座する寺院。約1300年の歴史を持つ。修験道の開祖「役の行者」によって開山され、御本尊「馬頭観世音菩薩」を祀る。和歌山県南部で最古・最大の開運・厄除の霊場とされ、あらゆる願掛けができるとされる。また、桜、あじさい、紅葉の名所として知られている。毎月行われている「護摩祈祷厳修」の他、年中行事として行われている祈願祭や供養会は誰でも自由に参加できる。
-
12位

善福院釈迦堂
和歌浦湾の南に広がる梅田の谷合にある天台宗の寺院。1327年日本に茶を伝えた栄西によって廣福寺五ヶ院の一つとして創建される。現在は国宝の釈迦堂のみが残されているが、安土桃山時代には加茂氏の菩提寺として七堂伽藍を有するほど栄えていたという。釈迦堂は裳階つきの禅宗仏殿で木割がやや太く、それでいて本瓦葦寄棟造や平行垂木など禅宗様の特色がよく見られるのが特徴。日本に現存する典型的な禅宗様仏殿としては鎌倉の円覚寺舎利殿や山口県の功山寺仏殿などと並び最古参のひとつとされる。
-
13位

粉河寺
近畿2府4県と岐阜県、約1000kmに及ぶ観世音菩薩(かんぜおんぼさつ)を巡礼する旅として知られる「西国三十三所」。およそ1300年前に起源をもつ日本最古の観音巡礼は、今もなお多くの人の心をひきつけてやまない。一番から順に巡って和歌山県内最後となるのが、第三番札所・粉河寺だ。
-
14位

日前神宮・國懸神宮(日前宮社務所)
日前宮駅から徒歩で約1分、和歌山インターチェンジから車で約5分。創建2600年を超える由緒ある神社で、日前大神と國懸大神の祭神をそれぞれ祀る二つの大社が存在しているのが大きな特徴。主に縁結びや家内安全にご利益があるとされている。1月9日から11日にかけて「日前宮えびす詣り」が執り行われており、熊手や福俵といった縁起物が用意されるほか、赤いのぼりが並ぶ参道を夜に見られるのはこの時期ならでは。7月26日には神楽殿にて日前宮薪能も見られる。
-
15位

別格本山 一乗院
高野山の裾のに広がる高野山真言宗の寺院。高野山ケーブル高野山駅から南海りんかいバスに乗って千手院橋停留所下車すぐの場所にある。本尊は高野山唯一となる弥勒菩薩。弘仁年間に善化上人によって開基されたと伝えられる。昭和8年(1933)に再建された本堂は緻密な彫刻やきらびやかな欄干が特徴的である。宿坊も経営しており、温泉や精進料理を堪能することができる。また写経や阿息観を体験したり勤行で修行に励むほか、院内にある仏画や高野山の資料を鑑賞して知識を深めることも可能。
-
16位

一願寺
願い事が1つ叶うことで有名な「一願寺(福巖寺)」。いくつもの願いが頭をよぎるが、ここは思い切って1つに絞って参拝しよう。安珍と清姫の、心揺るがす恋のストーリーも知ることができる寺院でもある。
-
17位

奥之院参道
高野山の一の橋から弘法大師の御廟へと続くおよそ2kmの参道。樹齢約700年を超える杉の古木が生い茂り、道々には鎌倉時代から現代までおよそ20万基に及ぶ墓碑や慰霊塔が並ぶ。これらには武田信玄や上杉謙信、大岡越前や紀州徳川家など数多くの有名人の名前が見受けられる。観光協会が発行するガイドマップに供養塔の地図があり、目的の人物を探しながら奥の院を目指すのに役立つ。また参道の脇には燈籠が並び、夕暮れから灯される明かりの光景には神秘的な雰囲気が感じられる。
-
18位

長保寺
海南市下津町上にある寺院。1000年に一条天皇の勅願によって創建。境内には約1万坪にわたる紀州徳川家歴代の廟所があり、大名墓所としては全国一の規模を誇る。また法隆寺以外で唯一、本堂と多宝塔、大門が国宝に指定されている寺院である。
-
19位

興国寺
日高郡由良町にある臨済宗妙心寺派の寺で、安貞元年(1227)の創建当時は真言宗の「西方寺」を称していた。正嘉2年(1258)に禅寺へ改められ、後に臨済宗法燈派大本山となった名刹である。金山寺味噌や醤油、尺八の日本発祥地としても有名。寺宝は非公開であるが、鎌倉時代における頂相彫刻の最高傑作といわれる「法燈国師坐像」や「絹本著色法燈国師像」などの重要文化財を所蔵。1月の成人の日に行われる「天狗まつり」や8月15日の「火祭り」には多数の参拝客が訪れる。
-
20位

熊谷寺
桓武天皇の皇子葛原親王の御願で承和4年(837)に建立された寺院。真言宗の総本山のひとつ高野山にありながらも、法然上人二十五霊場の番外札所として数えられる。場所は高野山奥の院へ向かう一の橋口バス停そばにあり、現在は宿坊として参拝者を迎え入れている。寺の名前は平家物語に登場する熊谷直実に由来。彼が首を上げた平敦盛の菩提をここで弔っている。過去には浄土宗の開祖法然上人や浄土真宗の開祖親鸞聖人も逗留している。その際井戸の水鏡に映った法然・親鸞・直実の姿をそれぞれが像として彫刻。御尊像を園光堂に奉安しているという。
-
21位

女人高野(不動坂口女人堂 他)
816年(弘仁7)に弘法大師が開いた高野山は、女性の立ち入りが禁止されていた。しかし、女性たちの参拝を受け入れる「女人高野」と呼ばれる寺院が存在し、その代表例として和歌山の「慈尊院」や奈良の「室生寺」などがある。2020年(令和2)には、これら女人高野のストーリーが日本遺産に認定された。
-
22位

大門
高野山に広がる寺院群の入口にそびえる高さ約25.1mの朱色に塗られた総門。開創当時は現在より下の九十九折谷に鳥居を建てて総門としていたが山火事や落雷で焼失。現在の大門は1705年に再建されたものである。見どころは門の左右に置かれた金剛力士像。大きさが東大寺南大門に次いで2番目と言われ、強くにらんだ眼差しと筋骨隆々とした肉体には迫力がある。また大門正面の柱に掲げられた「日々影向文」には今も弘法大師が私達を救ってくださるという意味があり、高野山の教えである同行二人信仰を表している。
-
23位

根來寺 国宝 大塔
高野山の学僧でもあった覚鑁上人によって開創された新義真言宗の総本山「根來寺」の境内にある、高さ36mにもなる日本最大級の木造多宝塔。真言密教の教義を形として表した建物で、天文16年(1547)に完成。豊臣秀吉による紀州征伐の焼き討ちは免れたが、当時を物語る火縄銃の弾痕が今でも残っている。国宝に指定されており、中に入って参拝することができる。
-
24位

温泉寺
龍神温泉バス停から徒歩で約5分。龍神温泉元湯の道を挟んで向かい側、難陀龍王社のすぐ左にある寺院。弘仁年間に難蛇龍王のお告げを受けた弘法大師によって温泉が発見され、薬師如来を安置。その後、僧の明算が龍王社薬師堂を再建した際に温泉寺と名付けられた。温泉街にあることから、多くの観光客が訪れるスポットとしても知られる。現在ある建物は近年に再建されたもの。
-
25位

根來寺
高野山に学び、弘法大師空海以来の才と称賛された平安後期の高僧・覚鑁上人(かくばんしょうにん)。わずか49歳で入滅するまで波乱万丈の人生の末に新義真言宗の礎を築き、没後に興教大師(こうぎょうだいし)の諡号(しごう)を授けられた真言宗中興の祖である覚鑁上人が、根來寺の開祖だ。
-
26位

奥之院
高野山の二大聖地のひとつで、空海(弘法大師)入定の地。空海が現在も瞑想していると言われる御廟がある。御廟に通じる約2kmの参道には、樹齢約700年の杉木立が続き、両側には皇族から庶民まで20万基以上の墓石や慰霊碑が並んでいる。御廟の手前にある燈篭堂も必見だ。堂内正面の祈親上人が献じた祈親灯と白河上皇が献じた白河灯は「消えずの火」として1000年以上燃え続けている。御廟に一番近い御廟橋より先は聖域のため、写真撮影は禁止されている。
-
27位

燈籠堂
高野山の二大聖地のひとつで、空海(弘法大師)入定の地である「奥之院」の御廟の手前に位置し、元々は御廟の拝堂として建立された。堂内には、参拝者が奉納した2万基以上の燈籠が所狭しと吊られている。堂内正面の祈親上人が献じた祈親灯と白河上皇が献じた白河灯は「消えずの火」として1000年以上燃え続けている。なかでも祈親灯は、貧しいお照という娘が自らの髪を売り、両親の菩提のために献じたものと伝えられ「貧女の一灯」とも呼ばれている。
-
28位

御影堂
御影堂は桁行15.1m梁間15.1mの向背付宝形造りをした建物。堂内外陣には弘法大師の十大弟子像が掲げられている。場所は高野山金剛峰寺金堂の裏手。もともとは弘法大師の持仏堂として建設された建物だが、大師の入定後に十大弟子のひとり真如親王が描いた大師の御影(絵画)を奉安して以来御影堂と名付けられたという。御影堂は高野山でも最重要の聖域と位置付けられ、御影は普段一般参拝者が見ることはできない。現在は旧暦3月21日に行われる「旧正御影供」の前夜、御逮夜法会の後にのみ外陣への一般参拝が可能である。
-
29位

本願寺日高別院(日高御坊)
紀州鉄道「西御坊駅」より徒歩5分。1540年に湯川直光が建立した浄土真宗本願寺派の名刹。豊臣秀吉の紀州攻めの際に焼失した後、現在地に移転してからは「御坊さん」と呼ばれ、御坊市の名の興りとなった。現在の本堂は1825年に再建されたもので、坊舎のほか、書院、鐘楼堂、四脚門、薬医門、太鼓楼などが残されている。周辺は江戸時代に寺内町として栄え、町並みには当時の面影が残る。境内の大イチョウは樹齢400年あまりになる県の天然記念物。
-
30位

補陀洛山寺
JR那智駅から徒歩で約3分のところにある寺院。9世紀から18世紀頃にかけて南海に存在すると信じられていた観音浄土を目指し、渡海上人が30日分の食糧と油を乗せて出航した補陀落渡海の出発点として知られる。平成16年(2004)には世界遺産「紀伊山地の霊場と参詣道」の一部に認定されているほか、本尊の「三貌十一面千手千眼観世音菩薩」も重要文化財となっている。敷地内には復元された補陀洛渡海船や渡海上人の墓が見られる。
-
8位

金剛三昧院
北条政子が夫・源頼朝と息子・実朝の菩提を弔うために建立した「金剛三昧院」は、国宝の多宝塔をはじめ数々の文化財を擁しており、世界遺産 「紀伊山地の霊場と参詣道」の構成資産ともなっている。鎌倉時代そのままの荘厳な雰囲気は参拝客を圧倒する。南海電鉄「極楽橋駅」からケーブルカーで約5分。
-
9位

東光寺
湯の峰温泉にある天台宗の寺院。高さ約3mの本尊「湯峯薬師」は、温泉の源泉の周囲で湯の花が自然に積って薬師如来の形となったものだと伝わっている。約1800年前、裸形上人が薬師如来の胸に空いた穴から温泉が湧きだしているのを見出したという。毎年1月8日には、「八日薬師祭」が行われ、温泉の湯を献湯し、湯の峰温泉の繁栄と参拝者の諸願成就を祈願する。
-
10位

道成寺
日高川町鐘巻にある大宝元年(701)創建の和歌山県最古の寺院。講堂の本尊である千手観音像は1300年以上の歴史を誇る日本でも最も古いもののひとつ。これを含め宝佛殿では国宝3点、重要文化財11点、県指定文化財4点の貴重な仏像を年間を通じて参拝することができる。
-
11位

救馬溪観音
南紀白浜温泉街から車で約25分の所に鎮座する寺院。約1300年の歴史を持つ。修験道の開祖「役の行者」によって開山され、御本尊「馬頭観世音菩薩」を祀る。和歌山県南部で最古・最大の開運・厄除の霊場とされ、あらゆる願掛けができるとされる。また、桜、あじさい、紅葉の名所として知られている。毎月行われている「護摩祈祷厳修」の他、年中行事として行われている祈願祭や供養会は誰でも自由に参加できる。
-
12位

善福院釈迦堂
和歌浦湾の南に広がる梅田の谷合にある天台宗の寺院。1327年日本に茶を伝えた栄西によって廣福寺五ヶ院の一つとして創建される。現在は国宝の釈迦堂のみが残されているが、安土桃山時代には加茂氏の菩提寺として七堂伽藍を有するほど栄えていたという。釈迦堂は裳階つきの禅宗仏殿で木割がやや太く、それでいて本瓦葦寄棟造や平行垂木など禅宗様の特色がよく見られるのが特徴。日本に現存する典型的な禅宗様仏殿としては鎌倉の円覚寺舎利殿や山口県の功山寺仏殿などと並び最古参のひとつとされる。
-
13位

粉河寺
近畿2府4県と岐阜県、約1000kmに及ぶ観世音菩薩(かんぜおんぼさつ)を巡礼する旅として知られる「西国三十三所」。およそ1300年前に起源をもつ日本最古の観音巡礼は、今もなお多くの人の心をひきつけてやまない。一番から順に巡って和歌山県内最後となるのが、第三番札所・粉河寺だ。
-
14位

日前神宮・國懸神宮(日前宮社務所)
日前宮駅から徒歩で約1分、和歌山インターチェンジから車で約5分。創建2600年を超える由緒ある神社で、日前大神と國懸大神の祭神をそれぞれ祀る二つの大社が存在しているのが大きな特徴。主に縁結びや家内安全にご利益があるとされている。1月9日から11日にかけて「日前宮えびす詣り」が執り行われており、熊手や福俵といった縁起物が用意されるほか、赤いのぼりが並ぶ参道を夜に見られるのはこの時期ならでは。7月26日には神楽殿にて日前宮薪能も見られる。
-
15位

別格本山 一乗院
高野山の裾のに広がる高野山真言宗の寺院。高野山ケーブル高野山駅から南海りんかいバスに乗って千手院橋停留所下車すぐの場所にある。本尊は高野山唯一となる弥勒菩薩。弘仁年間に善化上人によって開基されたと伝えられる。昭和8年(1933)に再建された本堂は緻密な彫刻やきらびやかな欄干が特徴的である。宿坊も経営しており、温泉や精進料理を堪能することができる。また写経や阿息観を体験したり勤行で修行に励むほか、院内にある仏画や高野山の資料を鑑賞して知識を深めることも可能。
-
16位

一願寺
願い事が1つ叶うことで有名な「一願寺(福巖寺)」。いくつもの願いが頭をよぎるが、ここは思い切って1つに絞って参拝しよう。安珍と清姫の、心揺るがす恋のストーリーも知ることができる寺院でもある。
-
17位

奥之院参道
高野山の一の橋から弘法大師の御廟へと続くおよそ2kmの参道。樹齢約700年を超える杉の古木が生い茂り、道々には鎌倉時代から現代までおよそ20万基に及ぶ墓碑や慰霊塔が並ぶ。これらには武田信玄や上杉謙信、大岡越前や紀州徳川家など数多くの有名人の名前が見受けられる。観光協会が発行するガイドマップに供養塔の地図があり、目的の人物を探しながら奥の院を目指すのに役立つ。また参道の脇には燈籠が並び、夕暮れから灯される明かりの光景には神秘的な雰囲気が感じられる。
-
18位

長保寺
海南市下津町上にある寺院。1000年に一条天皇の勅願によって創建。境内には約1万坪にわたる紀州徳川家歴代の廟所があり、大名墓所としては全国一の規模を誇る。また法隆寺以外で唯一、本堂と多宝塔、大門が国宝に指定されている寺院である。
-
19位

興国寺
日高郡由良町にある臨済宗妙心寺派の寺で、安貞元年(1227)の創建当時は真言宗の「西方寺」を称していた。正嘉2年(1258)に禅寺へ改められ、後に臨済宗法燈派大本山となった名刹である。金山寺味噌や醤油、尺八の日本発祥地としても有名。寺宝は非公開であるが、鎌倉時代における頂相彫刻の最高傑作といわれる「法燈国師坐像」や「絹本著色法燈国師像」などの重要文化財を所蔵。1月の成人の日に行われる「天狗まつり」や8月15日の「火祭り」には多数の参拝客が訪れる。
-
20位

熊谷寺
桓武天皇の皇子葛原親王の御願で承和4年(837)に建立された寺院。真言宗の総本山のひとつ高野山にありながらも、法然上人二十五霊場の番外札所として数えられる。場所は高野山奥の院へ向かう一の橋口バス停そばにあり、現在は宿坊として参拝者を迎え入れている。寺の名前は平家物語に登場する熊谷直実に由来。彼が首を上げた平敦盛の菩提をここで弔っている。過去には浄土宗の開祖法然上人や浄土真宗の開祖親鸞聖人も逗留している。その際井戸の水鏡に映った法然・親鸞・直実の姿をそれぞれが像として彫刻。御尊像を園光堂に奉安しているという。
-
21位

女人高野(不動坂口女人堂 他)
816年(弘仁7)に弘法大師が開いた高野山は、女性の立ち入りが禁止されていた。しかし、女性たちの参拝を受け入れる「女人高野」と呼ばれる寺院が存在し、その代表例として和歌山の「慈尊院」や奈良の「室生寺」などがある。2020年(令和2)には、これら女人高野のストーリーが日本遺産に認定された。
-
22位

大門
高野山に広がる寺院群の入口にそびえる高さ約25.1mの朱色に塗られた総門。開創当時は現在より下の九十九折谷に鳥居を建てて総門としていたが山火事や落雷で焼失。現在の大門は1705年に再建されたものである。見どころは門の左右に置かれた金剛力士像。大きさが東大寺南大門に次いで2番目と言われ、強くにらんだ眼差しと筋骨隆々とした肉体には迫力がある。また大門正面の柱に掲げられた「日々影向文」には今も弘法大師が私達を救ってくださるという意味があり、高野山の教えである同行二人信仰を表している。
-
23位

根來寺 国宝 大塔
高野山の学僧でもあった覚鑁上人によって開創された新義真言宗の総本山「根來寺」の境内にある、高さ36mにもなる日本最大級の木造多宝塔。真言密教の教義を形として表した建物で、天文16年(1547)に完成。豊臣秀吉による紀州征伐の焼き討ちは免れたが、当時を物語る火縄銃の弾痕が今でも残っている。国宝に指定されており、中に入って参拝することができる。
-
24位

温泉寺
龍神温泉バス停から徒歩で約5分。龍神温泉元湯の道を挟んで向かい側、難陀龍王社のすぐ左にある寺院。弘仁年間に難蛇龍王のお告げを受けた弘法大師によって温泉が発見され、薬師如来を安置。その後、僧の明算が龍王社薬師堂を再建した際に温泉寺と名付けられた。温泉街にあることから、多くの観光客が訪れるスポットとしても知られる。現在ある建物は近年に再建されたもの。
-
25位

根來寺
高野山に学び、弘法大師空海以来の才と称賛された平安後期の高僧・覚鑁上人(かくばんしょうにん)。わずか49歳で入滅するまで波乱万丈の人生の末に新義真言宗の礎を築き、没後に興教大師(こうぎょうだいし)の諡号(しごう)を授けられた真言宗中興の祖である覚鑁上人が、根來寺の開祖だ。
-
26位

奥之院
高野山の二大聖地のひとつで、空海(弘法大師)入定の地。空海が現在も瞑想していると言われる御廟がある。御廟に通じる約2kmの参道には、樹齢約700年の杉木立が続き、両側には皇族から庶民まで20万基以上の墓石や慰霊碑が並んでいる。御廟の手前にある燈篭堂も必見だ。堂内正面の祈親上人が献じた祈親灯と白河上皇が献じた白河灯は「消えずの火」として1000年以上燃え続けている。御廟に一番近い御廟橋より先は聖域のため、写真撮影は禁止されている。
-
27位

燈籠堂
高野山の二大聖地のひとつで、空海(弘法大師)入定の地である「奥之院」の御廟の手前に位置し、元々は御廟の拝堂として建立された。堂内には、参拝者が奉納した2万基以上の燈籠が所狭しと吊られている。堂内正面の祈親上人が献じた祈親灯と白河上皇が献じた白河灯は「消えずの火」として1000年以上燃え続けている。なかでも祈親灯は、貧しいお照という娘が自らの髪を売り、両親の菩提のために献じたものと伝えられ「貧女の一灯」とも呼ばれている。
-
28位

御影堂
御影堂は桁行15.1m梁間15.1mの向背付宝形造りをした建物。堂内外陣には弘法大師の十大弟子像が掲げられている。場所は高野山金剛峰寺金堂の裏手。もともとは弘法大師の持仏堂として建設された建物だが、大師の入定後に十大弟子のひとり真如親王が描いた大師の御影(絵画)を奉安して以来御影堂と名付けられたという。御影堂は高野山でも最重要の聖域と位置付けられ、御影は普段一般参拝者が見ることはできない。現在は旧暦3月21日に行われる「旧正御影供」の前夜、御逮夜法会の後にのみ外陣への一般参拝が可能である。
-
29位

本願寺日高別院(日高御坊)
紀州鉄道「西御坊駅」より徒歩5分。1540年に湯川直光が建立した浄土真宗本願寺派の名刹。豊臣秀吉の紀州攻めの際に焼失した後、現在地に移転してからは「御坊さん」と呼ばれ、御坊市の名の興りとなった。現在の本堂は1825年に再建されたもので、坊舎のほか、書院、鐘楼堂、四脚門、薬医門、太鼓楼などが残されている。周辺は江戸時代に寺内町として栄え、町並みには当時の面影が残る。境内の大イチョウは樹齢400年あまりになる県の天然記念物。
-
30位

補陀洛山寺
JR那智駅から徒歩で約3分のところにある寺院。9世紀から18世紀頃にかけて南海に存在すると信じられていた観音浄土を目指し、渡海上人が30日分の食糧と油を乗せて出航した補陀落渡海の出発点として知られる。平成16年(2004)には世界遺産「紀伊山地の霊場と参詣道」の一部に認定されているほか、本尊の「三貌十一面千手千眼観世音菩薩」も重要文化財となっている。敷地内には復元された補陀洛渡海船や渡海上人の墓が見られる。
エリアで絞り込む FILTER BY AREA
人気の記事 POPULAR NEWS
-

神戸の人気観光スポットおすすめ30選|外せない定番・名所から穴場まで見どころ満載の観光地を紹介
おでかけ 兵庫 旅行 -

新潟の人気観光スポットおすすめ20選|外せない定番・名所から穴場まで見どころ満載の観光地を紹介
おでかけ 中部 新潟 -

長崎の人気観光スポットおすすめ30選|外せない定番・名所から穴場まで見どころ満載の観光地を紹介
おでかけ 九州 旅行 -

宮崎の人気観光スポットおすすめ20選|外せない定番・名所から穴場まで見どころ満載の観光地を紹介
おでかけ 九州 宮崎 -

滋賀の人気観光スポットおすすめ20選|外せない定番・名所から穴場まで見どころ満載の観光地を紹介
おでかけ 旅行 滋賀 -

鳥取の人気観光スポットおすすめ20選|外せない定番・名所から穴場まで見どころ満載の観光地を紹介
おでかけ 中国 旅行 -

秋田の人気観光スポットおすすめ20選|外せない定番・名所から穴場まで見どころ満載の観光地を紹介
おでかけ 旅行 東北 -

和歌山の人気観光スポットおすすめ20選|外せない定番・名所から穴場まで見どころ満載の観光地を紹介
おでかけ 和歌山 旅行